昨年10月、『円光物に想う』と題した漆蒔絵パネルを奉納した際、中尊寺発刊の寺報に文章を寄稿してくれないかとのご依頼がありましたので、慣れないながら正月に書きました。
年一回の寺報らしく、3月送られてきましたので、これも私自身の記録・記念に残しておきます。
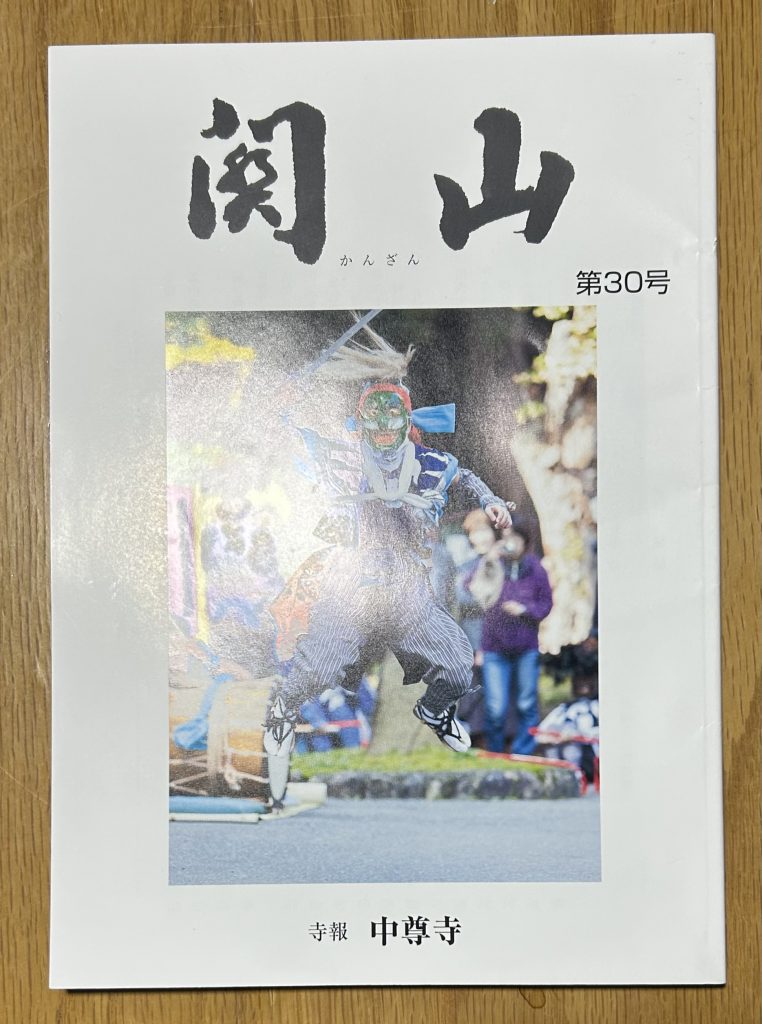
円光仏に想う
令和7年1月
伊藤 猛
はじめに・・
昨年10月28日、藤原秀衡公の御命日に、私の描きました“円光仏に想う”と題した漆蒔絵パネルを、様々なご縁から中尊寺金色堂建立900年の節目の年に奉納させて頂きました。それは、誠にありがたく光栄なことであり感謝申し上げます。
中尊寺は、私が棲居し仕事をしております信州木曽より、車で700キロほどの距離があり、なかなか訪れるのが大変なため、奉納の時で4度目の参拝となりました。過去4回の参拝の内、2度目の参拝は、私の大学時代の恩師であり、中尊寺金色堂の昭和の解体大修理の際、漆部門の修理復元に携わった大場松魚先生(人間国宝)がお亡くなられた2012年でした。その折には、2011年の東北大震災の鎮魂と、亡き先生を偲んでお参りさせて頂きました。
大場先生からは、金沢美術工芸大学在学中、中尊寺金色堂の修理復元のお話をよく聞かされておりましただけに、私にとって中尊寺は、全国にあるどこのお寺より足を運び参拝することになった特別なお寺です。思うに、金色堂は、私達漆職人にとって、遥か昔の漆工人の技量はもとより、昭和の大修理にあたった先人のあくなき職人魂を感じることができるもので、平安時代のまさに黄金に輝く漆の建造物であり、その存在は、私にとって、何より漆の仕事をしていての励みであり、仕事に誇りを感じさせ、さらなる探求心をかきたてる存在です。
奉納した 漆蒔絵パネル
漆建築の最高峰
日本の漆建築文化の歴史を振り返りますと、その最高峰は平安時代にあると私は考えています。
中尊寺一帯の伽藍は平安時代末期に、安倍氏と清原氏豪族の争いから、藤原清衡公の家族同士の凄惨な争いの後、戦乱で亡くなった人々への弔いと、戦い無き世を願い、清衡公が建立された塔を始めとしたお堂の数々だと言われています。
その中でも、金色堂には御本尊の阿弥陀如来座像を始めとする多くの立像が配され、金箔で覆われ、金銀粉をあしらった蒔絵、南方の海から採られた夜光貝による螺鈿細工、さらには琥珀を始めとした宝玉も埋め込まれるなど、荘厳な装飾が施されております。まさに漆建造物の頂点に相応しいと思います。さらに、その須弥壇の中には藤原4代の亡骸が漆塗りの棺の中にミイラとして安置されているという実にミステリアスで驚きのお堂でもあります。
ご奉納の際、本堂で秀衡公の御命日の法要をした後、金色堂ガラススクリーン内に入り、奉納した額装画を立て、ご焼香をさせて頂きましたこと、誠に恐縮の至りでした。そして、内陣を前に身を置いた時、何とも言えない静寂な空気感を味わうと共に、現在の不穏な世界情勢と、私事ではありますが、年老いていく95歳の母のことを想いながら、あらゆるものの平穏無事を祈らずにいられませんでした。
中尊寺金色堂こそは、それが創り出す精神世界も含めて、平安時代から今日に至るまでの漆建造物の最高峰と改めて体感いたしました。
まだ捨てたもんじゃない=一期一会
さて、ここからは少し、私のこれまでの漆にかかわる活動や想いと、それがどう円光仏へと至って来たかを、お話しさせていただこうと思います。
小さい頃から漆に囲まれ育ってきた私は、幸運にもこれまで、様々な人、物との出会いから実に我儘な物創りをさせていただくことができました。振り返って、とても感謝しております。
大学の卒業制作では、“この世に生まれし者に幸あれ!まだ捨てたもんじゃないさ!”の副題をつけた卒業制作を創りました。そして、それから待ち受けている厳しい人間社会に、その言葉を頼りに卒業しました。
それは今でも続いている私の精神的な支えのひとつとなっています。生きていれば嫌なことも多々あり、苦しみも喜びと同様にあります。そんな時、それでもまだまだ捨てたもんじゃない!と自分に言い聞かせ、何とか今でも生かさせて頂いております。
そんな私ですが、美大卒業後、家業を継ぐべく、故郷の木曽に帰りました。それから3年経つのを待たず翌々年の正月2日に父が62歳で早逝しました。父は死の直前、5時間ほど前に、「一期一会」という書を記し、私に残してくれました。

生前中、父は事あるごとに私に「お金は残せないが、人は残してやる。」と、言っていました。本当にそうなの・・・と、半信半疑でありましたが、亡くなってみると確かに大勢の人達が私の周りに居て、その後の人間関係におきましてそうそう困ることもなく、家業の仕事もそれなりにこなすことが出来ました。亡き父に感謝です。
人との繋がり=長野オリンピックメダル
美大を卒業して間も無く、現在プリンター製作等で有名なセイコーエプソン社(当時の諏訪精工舎)から、『金属に漆を塗ることが出来るか?』との問い合わせがありました。それは、父の大学の後輩にあたる草間三郎様(後にセイコーエプソンの社長になりました。)からのものでした。
卒業制作におきまして、少しばかり金属に漆を焼き付け塗ることをしてきましたので、『出来ると思います。』と言うと、幸運にもその研究開発に携わることとなり、父が亡くなりました後、父の供養を兼ね、漆蒔絵提げ時計3000個を無事納品することが出来ました。
これも、父の残してくれた人の繋がりという財産から生まれたものだと思います。
そして、その技術と金属との出会いから、1998年には勝者の胸にかけられました長野オリンピック漆メダルの道が開かれていったのであります。
メダルを手掛けることはある意味とても光栄なことでしたが、栄あるオリンピックメダルを私のような名もなきかけ出しの漆職人が提案者としてプレゼンテーションから交渉、本制作まで若き職人達と仕事をすることになったものですから、その後、それを巡る軋轢も生じ、苦しむこともありました。
人間とは善かれと思ってしたことも、ある人間にとっては出過ぎになってしまうこともあります。しかし、そうでもしなくては国家の威信をかけてのオリンピックメダルは実現しなかったと考えています。何故なら、これまで日本開催のオリンピックメダルは、先の2021年開催された東京オリンピック含め全て国主導の造幣局が制作してきているのですから。
いずれにしてもオリンピック史上、最も美しいメダルと時に言ってもらえるような、夢に描いた漆のメダルが実現しましたことは、私にとってとても貴重な体験でした。そして、大きな誇りと共に責任を負うことになりました。両者を共に負いつつ、幸か不幸か、今でも悩ましい日々を過しております。
しかし、この時の体験によって、私は何よりも、『自分の中で想像できることは、様々な困難は伴うが必ず出来る!』という確信めいたものを手に入れることがきたと思います。


さらに様々な人・物との出会い=円光仏へ
今回の奉納で描きました菩薩像は、中尊寺金色堂内陣4本の巻柱に描かれた4 8 体のうちの一体の菩薩像であります。その一体の菩薩像をあえて“円光仏”と命名させて戴きました。金属光背を配した菩薩像。円柱の巻柱に全てがまるく治まるよう、まるで太陽の中で菩薩様が光を放っているように見えたのです。その菩薩様も、すでに900年という長い時を経て今では仏様に仲間入りしたことでしょう。
ところで、私は、20年ほど前から大きなお仏壇ではなく、現代に即した祈りの形としてのコンパクトなお厨子を制作してきました。そこに自分なりのご本尊を入れれば、幕末、篤姫が薩摩藩から徳川家にお輿入れをした際に持参したと言われるお厨子のように簡単に持ち運びが出来、ご先祖を弔い、自分を律する仏壇になりうると考えたからです。
そんなある日、知人宅を訪ねましたところ、不思議な物を見せて頂きました。話を聞くと、それは中国西域にあるキトラ石窟の壁画から剥ぎ取られた観音菩薩像の盗掘品だと言うことでした。どこか怪し気な話しでしたが、これもとてもミステリアスで気になり、当時制作したばかりの文字盤に蒔絵を施した腕時計と交換して欲しいと願い出て了承され、持ち帰りました。いまだ本物かどうかは定でありませんが、とにかくそれが偽物であったとしても、私にはどうでもいいのです。早速、その壁画の菩薩像を黒い漆塗りの板に嵌め込み、厨子の中に納めました。これがなかなかいい。その前に小さな本尊でも安置してやれば最高!と厨子が出来上がり、ひとり無邪気に悦にいっておりました。
その後、2度目の中尊寺参拝から間も無く、美大の後輩が訪ねてくれました。何でも私の毎日書き溜めてきた300のほどのブログを読み、2度目の中尊寺訪問を知り興味深かったとのことでした。私はそれまで彼とは面識がなく、初めてお会いした人でしたが、彼こそ、中尊寺を始め日光東照宮の修復を手がけ、今回の奉納にご尽力頂きました小西美術工芸社の岩本元さんでした。
そこで、様々な話しをし、厨子に納まっている壁画をお見せしていると、多賀城市にある東北歴史博物館開館にあたって彼が制作した中尊寺の巻柱に描いた菩薩像の試作品の手板が、手元にあるので送ってくれると言ってくれました。彼が帰り、早速手板に描かれた菩薩像を送ってくれ拝見すると、これが寸分違わず、私の作った厨子の中に納まってしまいました。
いい加減に返さないといけないなあと思いつ、菩薩様も居心地がさぞ良かったのか居座り、それから5年が経過した2018年、東京での還暦の個展の際にお返しした次第です。
しかし、なくなってしまうと、空き家になった厨子が寂しいもので、今度は自分の手で出来ないものか!?と私の中で想いが募ります。しかし、問題は私に描けるかです。地元の蒔絵師に聞いてみても難しい、自信がないという。なかなか難題でした。
時を経て、昨年(2023年)春、一念発起し、国立博物館内にある岩本さんの工房を訪ね、やりたい旨を伝えました。そして、岩本さんらが1999年一億円で制作したというレプリカの中尊寺金色堂巻柱(一本の柱には12体の蒔絵菩薩像が描かれています)を観るべく多賀城市の東北歴史博物館を訪ね、その足で3度目となる中尊寺に行き、これより制作したい意を伝える為お参りさせて頂きました。
私に出来るかどうかは未知、ただ単純に作ってみたかったのです。しかし、やってみると何とか出来上がるものですね。人間の意思の力とは、まんざら捨てたものじゃないようです。そうして出来上がってはみたものの、とにかく平安時代の蒔絵を再現したく、あえて今ある最も荒い金粉を使いましたが、当時のような金塊を鑢で擦り下ろして作った金粉の様子とは違うであろうし・・・。はたまた創建当時の金蒔絵の輝きの様子は、復元したものを観ても明確ではなく謎でありますし・・・。現在、出来うることであれば平安時代と同じ様に、金塊を鑢で擦り下ろした自作の金粉を使用し、いつの日かもう一度、より高い創作に挑戦したいものだと考えている。そんな毎日です。

最後に・・・
私は今年で67歳を迎えますが、これまで山深い木曽の地に住みながら、漆塗り時計、お椀を始めとした器物、オリンピックメダル、オルゴール、厨子等、様々な物を創ってきました。それらも全て人・物・自然・旅での出会いから生まれてきた物たちです。
今回、その一つとして“円光仏に想う”と名付けた蒔絵菩薩像の額装画が加わり、奉納できましたことを嬉しく思います。そして、これもまた、これまで書いてきましたように、様々な出会いと不思議なご縁があったからと振り返り、感謝するばかりであります。
これからの残り少ない人生も、「一期一会」を大切にし、「困難でも想像することはきっとカタチにできる」という気持ちを持って、生き抜ければ。などと思っております。
ありがとうございました。
合掌
